この本を閉じるころ、あなたの耳にはどんな音が残っているだろう。 コオロギの声か、海の泡の音か、それとも静かな呼吸か。 私がこの「せいかつ生き物図鑑」を描きはじめた理由は、 生き物そのものよりも、そこに流れる“生活の気配”を記録したかったからだ。
マアジの海から始まった旅は、 いつしか野原に降りて、コオロギの声を聴くようになった。 魚たちは光の中で生き、虫たちは闇の中で語る。 彼らはどちらも、人の暮らしを照らす“鏡”だった。
🌊 海と陸のあいだにあるもの
鯵を描いたとき、私は“群れの中の孤独”を見た。 コオロギを書いたとき、私は“静寂の中のつながり”を聴いた。 それは相反するようでいて、どちらも「生きている」という一点で重なる。 海にいる者も、陸にいる者も、 同じ世界の“呼吸”をしている。
このシリーズでは、 科学的な正確さと文学的な余韻、その両方を持たせたかった。 生き物はデータではなく、光や風や音の中に存在している。 その一瞬の気配を、言葉の中に残しておきたかった。
🪶 聴くことの哲学
「聴く」という行為には、静けさが必要だ。 それは黙って世界を見つめること。 何も語らず、ただ風と同じ時間を生きること。 人はそこに“他者”を感じる。 虫の声も、波の音も、 それを聴く瞬間にだけ、私たちは自然の一部になる。
この図鑑が伝えたかったのは、 生き物の知識ではなく、生き物との“距離感”だった。 触れず、支配せず、ただ共に在る。 それがこの時代の新しい風流かもしれない。
🌕 次の旅へ
次に描くのは、海のその先―― 「海を見つめる魚」の続編である“静かな命の記録”になる。 それはもう図鑑ではなく、 生き物と人との記憶を結ぶ“詩集”のようなものになるだろう。
あなたがこのページを閉じたあとも、 風の中で、夜の草むらで、 小さな音を探すことがあるなら、 この本はまだ生きている。
🪶 終章の詩
風の中 名もなき声を ひとつ聴く 世界はいまも 静かに息づく

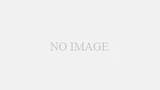

コメント