🪸 基本情報
私たちの食卓に並ぶアジ。
その一匹一匹は、海と風と潮を知り尽くした漁師たちの手によって獲られています。
「定置網」と「一本釣り」――日本のアジ漁を支える二つの伝統漁法。
本記事では、漁師たちの知恵と工夫、そして現代の海に生きる姿を紹介します。
🌊 定置網漁 ― 海の流れを読む“待つ漁”
定置網漁は、アジ漁の代表的な手法です。
沖合に大きな網を固定し、魚が潮の流れに乗って入ってくるのを待つという“受け身の漁”。
しかし、その成功には海の読みと経験が欠かせません。
漁師たちは、潮の向き・水温・月齢・風向きを毎日記録。
「今日は南風が強いから、アジは岸寄りに来る」「水温が上がったから深場へ下がる」――
そんな判断を積み重ねて、網を仕掛ける位置や深さを微調整します。
夜明け前、船で網を引き上げる瞬間、
銀色のアジが一斉に跳ね上がる光景は、まさに“海の恵み”そのもの。
この定置網漁こそ、自然のリズムを読む知恵の結晶なのです。
🎣 一本釣り ― 技と瞬発力の“攻める漁”
一方の一本釣りは、“漁師の腕前”がすべて。
魚群探知機を使いながら群れを見つけ、竿一本で次々と釣り上げます。
特に九州・大分県の佐賀関では、
「関あじ」と呼ばれるブランドアジがすべて一本釣りで漁獲されています。
この方法では、魚に傷がつかず、ストレスが少ないため、
身が締まり、味も格別。
漁師はアジの動きを見ながら、
「潮が速いときは仕掛けを軽く」「太陽が昇る前は深めに」など、
経験で得た“海の呼吸”を読み取って動きます。
また、一本釣りは環境への負荷が少なく、
サステナブル(持続可能)な漁法としても注目されています。
⚙️ 現代漁業の進化 ― 技術と伝統の融合
近年では、漁業の現場にもテクノロジーが導入されています。
GPSや海洋センサーを活用して、
水温・潮流・魚群の位置をリアルタイムで把握。
AIが「今日アジが集まりやすい海域」を予測する試みも始まっています。
しかし、どれほど技術が進んでも、
最終的に漁を決めるのは“漁師の感覚”です。
「潮の匂い」「波の立ち方」「風の音」――
それらを身体で感じ取る力が、今もなお現場では生きています。
🧩 地域と共に生きる漁業
アジ漁は、単なる仕事ではなく、地域の暮らしそのものです。
長崎県松浦市では、港ごとに漁師が協力し、
定置網を共同管理する「浜組(はまぐみ)」という仕組みがあります。
漁に出る人、港で仕分ける人、販売する人。
そのすべてが連携して、地域全体で“海と共に生きる”仕組みを作っています。
また、観光業とも結びつき、
「漁師体験ツアー」「港の朝市」などを通じて、
若い世代や観光客にも“海の仕事”を伝える活動が広がっています。
🌅 まとめ ― 海を知り、人をつなぐ漁の知恵
アジを獲るという行為は、単なる漁業ではなく、人と自然の対話です。
海を読み、風を感じ、仲間と力を合わせて魚を届ける――。
そこには、日本の漁師たちが積み重ねてきた暮らしの哲学があります。
銀色に光るアジの群れは、
今日もその知恵と技の結晶として、私たちの食卓に届いているのです。
次回は「鯵24:鯵の旬と漁期 ― 季節ごとの味の変化」で、
海のリズムと味覚のサイクルを見ていきましょう。

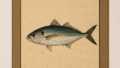

コメント